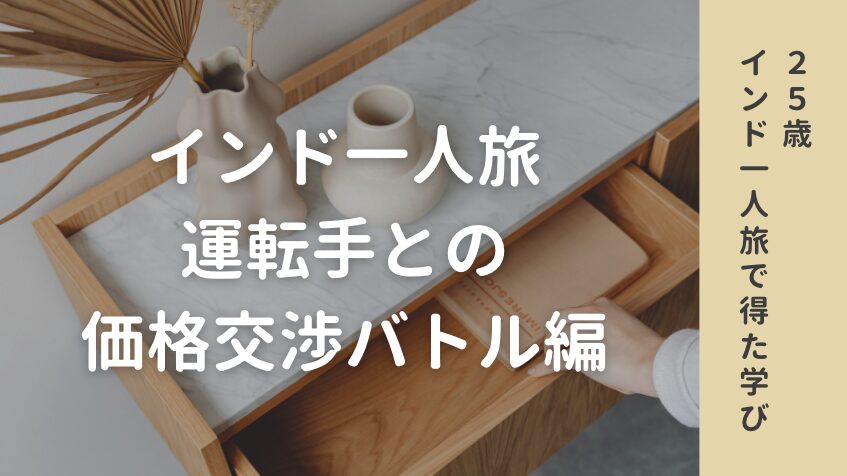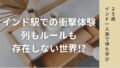1. 旅の中で一番腹が立った瞬間
インドでの旅の中で、一番腹が立ったのは、間違いなくリキシャのドライバーたちとのやり取りでした。
日本の常識が全く通じない国だとは覚悟していたけれど、それでも「ここまでか…」と思わされるほど、現実は想像を超えていました。

2. デリーの街で起きた出来事
最初の出来事はデリーの街中でした。
150ルピーで「ここまで行って」と伝え、前払いも済ませていました。リキシャのエンジンがガタガタと音を立てながら走り出し、途中までは何事もなく進んでいました。
しかし、目的地までまだ少し距離があるというところでドライバーが突然止まり、「ここまでだ」と言いました。
「いや、あと少し先だよ」と伝えると、「もうここから歩ける」と返されました。
仕方なく降りると、大通りを一本越えなければならず、炎天下の中を20分ほど歩く羽目になりました。
日本だと目的地までしっかり送ってくれるのに、インドでは平気で数十分歩かされる。
運転手の気分で、車を引き返しやすい場所で止められる。
「これがこの国の“普通”なのか」と思いました。

3. 終わりの見えない駆け引き
翌日も別のドライバーと交渉しました。
行き先を伝えると「500ルピー」と言われました。前日に調べていた相場では100ルピー。明らかに法外な価格です。
「100ルピーで行けますか?」と聞くと、ドライバーは笑いながら「燃料が高いから無理だ、100ルピーではどこもいけない」と言いました。
しかし私も譲らず、400ルピー、300ルピーと価格交渉を重ね、最終的には「じゃあ200ルピーで」となんとか折り合いをつけて出発しました。
ところが到着すると、「やっぱりもう少しかかる」「俺の運転良かっただろ」など何かと理由をつけて追加のルピーを要求してきます。日本ではあり得ないやりとりですが、インドでリキシャに乗ると、これが1人2人ではなく、皆当たり前かのようにふっかけてきます。
人によっては何も言わず到着後に勝手に金額を変えて要求してくる運転手も平気でいます。
その瞬間、またか…と思いました。
「最初に200ルピーって言ったはずだよ」と伝えますがなかなか相手も引き下がりません。額にしたら数百円なので、そのくらい払えよって思うかもしれません。私自身もいいサービスを受けたらチップも払います。
大事なのは金額ではなく、「観光客だからカモれそう」という雰囲気、表情丸出しで言い寄ってくる点。ここで言われるがまま払ってしまうと、「日本人はカモりやすい」というイメージを持たれてしまうため、私の後にインドに来る日本人が次から次にカモられていきます。
観光客である以上、現地価格よりはるかに何倍もの価格を最初にふっかけられますがそれに物怖じせず、日本人として舐められてたまるかというプライド、そしてこれから来る日本人にもインドを楽しんでほしいという思いで、このような一部のインド人とは納得できるまで交渉を続けたのを鮮明に覚えています。
しかしインド滞在中、数えられないほどのリキシャに乗りましたが、「前もって最初に伝えた金額で、かつ目的地まで正確に届けてくれる」運転手は珍しい、というかほぼほぼいないのが現実でした。
自由な国インドで、たとえ不条理でも彼らの中には彼らなりの“生きる理由”がある。
その自由さと図太さに、ある意味で人間の本能のような強さ、生きるための駆け引きを肌で感じました。
4. 声の大きさがすべてを決める国
タージマハルからアグラフォートへ向かうリキシャでは、70ルピーで乗せてもらったはずが、支払いの際に500ルピーを出したところ、運転手がまるで奪うように受け取り、お釣りを30ルピー少なく返してきました。
「お釣りが足りないよ」と伝えても、「細かいのもってないから」と笑ってごまかされて終わり。
金額の問題ではなく、誠実さを感じられなかったことに、心底腹が立ちました。
インドでは、言い合いが始まるとあっという間に野次馬が集まってきます。
周囲の人たちは状況を理解していなくても、声の大きい方に味方する。
冷静に話しても意味がない。
そんな現実を目の当たりにして、「ここでは正しさより勢いが勝つ国なんだ」と実感しました。
それでも、何度もこうしたことを経験しているうちに、感情が少しずつ変わっていきました。
最初の2回は、ただただ怒り。
けれど3回目、4回目になると、ある意味で“悟り”のようなものが訪れました。
「もう、これを受け入れよう。イライラしてたら旅が楽しめない。」
そう自分に言い聞かせました。
国が違えば、価値観も、仕事の仕方も、すべて違う。
いくら怒っても、相手に“悪気”があるわけではない。
ただ、そういう文化の中で生きているだけなのだと気づきました。
インドの人たちは、どこか“今”しか見ていません。
未来でも過去でもなく、目の前の瞬間を生きている。
それが時に無責任に見えるし、ずる賢く感じる。
でも、もしかしたらそれこそが、インド人の強さなのかもしれません。
5. インドという国を通して見えたもの
リキシャドライバーとのやり取りを通して学んだのは、「正しさや当たり前は国によってまるで違う」ということでした。
日本のように丁寧さや約束を重んじる文化は、インドでは通用しない。
でも、そうした混沌の中にも、彼らなりの生き方と理由があるのだと思いました。
砂埃の舞う街、排気ガスとスパイスの混ざったような生ゴミの匂い、そして絶え間ないクラクションの音。
そんな混沌の中で生きる人々の“たくましさ”と“図太さ”に、次第に感心するようになりました。
世界が違うというより、“生き方”そのものが違う。
人に対する気持ちの向け方も、日本とはまるで別の次元でした。
ある意味、笑えてくるほどです。
どんなに腹が立っても、それが日常として成り立っている。
そう考えると、怒りよりも「野生の人間らしさ、人間のたくましさ」を感じる1日になりました。
次回予告
デリーの喧騒の中で響くリキシャのエンジン音。
あの音を思い出すたびに、世界の広さと、自分の“当たり前”の小ささを思い知らされます。
旅は続く——次は、インドの魂が息づく街・バラナシへ。
次回、「バラナシ編」では、リキシャ騒動を乗り越えた僕が、ついに“インドの聖地”ガンジス川へと向かいます。
人生と死、祈りと混沌が入り混じるあの街で、言葉を失うような光景を目にしました。
ガンジス川のほとりで、目の前で火葬されていく光景、それを取り囲む人々、火葬場に漂う煙、その中で生きる“今を全うする人間”たち。
あの日、僕が感じた“生きる”ということの意味を、次の記事でお伝えします。
どうぞお楽しみに。
次回記事はこちらから↓
※