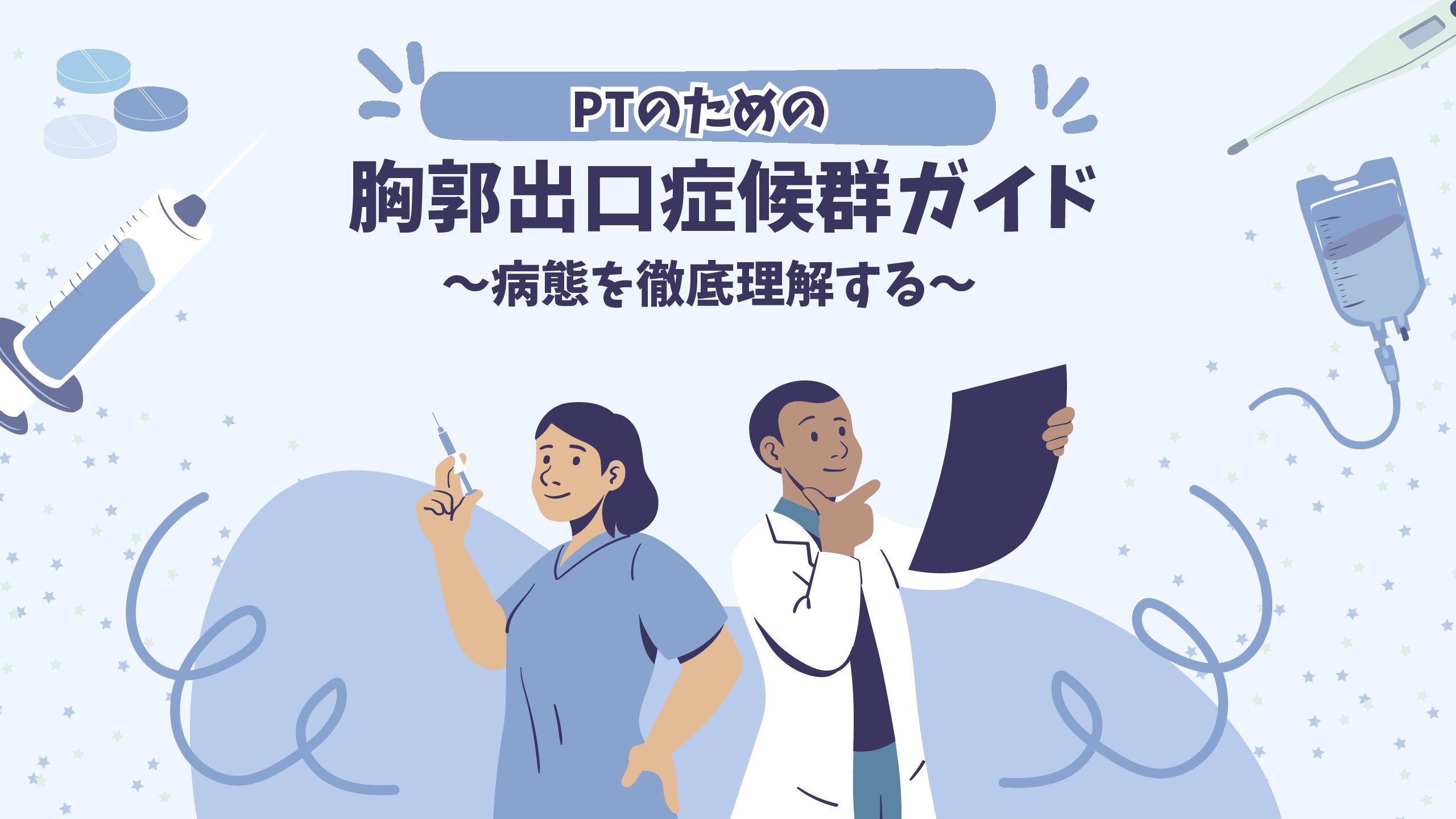胸郭出口症候群の絞扼部位:3つのトンネルを徹底解説
はじめに
胸郭出口症候群(Thoracic Outlet Syndrome:TOS)は、神経や血管が胸郭出口部で圧迫・絞扼されることにより、上肢や肩、頚部に多様な症状を呈する疾患群です。臨床現場において、鑑別診断やアプローチが難しいとされる本疾患に対して、理学療法士として正確な知識と評価力が求められます。本記事では、TOSの病態理解に欠かせない「3つの絞扼トンネル」について、エビデンスとともに詳しく解説します。特に理学療法学生や若手療法士に向けて、明日からの臨床に役立つ視点を提供します。
絞扼トンネル1:斜角筋隙(Scalene Triangle)
解剖学的構造
- 前斜角筋、
- 中斜角筋、
- 第1肋骨
この三者で形成される三角形の空間を「斜角筋隙」と呼びます。
通過する構造物
- 腕神経叢(C5〜T1)
- 鎖骨下動脈
※鎖骨下静脈はこのスペースを通らない点が重要。
病態と原因
前斜角筋や中斜角筋の過緊張、頚部筋群のアンバランス、第一肋骨の挙上により、腕神経叢や鎖骨下動脈が圧迫されることでTOSの症状が発生します。
エビデンス
Sanders RJ et al. (2007) によると、TOSのうち神経性TOS(Neurogenic TOS)が全体の約95%を占めており、その多くが斜角筋隙での圧迫に起因すると報告されています。
絞扼トンネル2:肋鎖間隙(Costoclavicular Space)
解剖学的構造
- 鎖骨(上)
- 第1肋骨(下)
- 鎖骨下筋や前斜角筋がスペースを狭小化させる要因に
通過する構造物
- 腕神経叢
- 鎖骨下動脈・静脈
病態と原因
猫背姿勢、デスクワークやスマホ操作による肩の前方突出、リュックや荷物の持ち方による圧迫など、日常動作による機械的な圧迫が主な原因とされます。
臨床評価のポイント
- 肩甲骨の前傾・下制による鎖骨の下降
- 鎖骨下筋の過緊張
エビデンス
Hoskins et al. (2010) によると、デスクワーカーのTOS有病率が高いことが明らかになっており、特に肋鎖間隙での圧迫による症状が多くみられています。
絞扼トンネル3:小胸筋下間隙(Subpectoralis Minor Space)
解剖学的構造
- 小胸筋の下
- 烏口突起
- 胸郭前面
通過する構造物
- 腕神経叢の一部
- 鎖骨下血管
病態と原因
小胸筋の過緊張、姿勢不良による短縮、リュックや肩掛けカバンなどの外的因子により、構造物が圧迫されることが多いです。長時間のデスクワークやスマートフォン使用による巻き肩姿勢も大きなリスク要因となります。
臨床でのサイン
- 小胸筋部の圧痛
- 小胸筋ストレッチで症状が軽減する
- アドソンテスト、ルーステストで陽性
エビデンス
Hardy et al. (2012) では、小胸筋下間隙での圧迫に起因するTOSを「Pectoralis Minor Syndrome」と分類し、その認知と対処の重要性を強調しています。
総まとめ:3つのトンネルを俯瞰して
| トンネル名 | 絞扼されやすい構造 | 主な原因 | 特徴的な臨床所見 |
|---|---|---|---|
| 斜角筋隙 | 腕神経叢・鎖骨下動脈 | 斜角筋の過緊張 | 神経症状が優位、頚部の動きに関連 |
| 肋鎖間隙 | 腕神経叢・鎖骨下血管 | 姿勢不良、鎖骨下筋の緊張 | デスクワーカーに多い、血流障害も起こりやすい |
| 小胸筋下間隙 | 腕神経叢・鎖骨下血管 | 巻き肩、リュックの使用 | 小胸筋ストレッチで軽減することあり |
まとめと臨床応用
胸郭出口症候群の評価・介入においては、どのトンネルでの絞扼が疑われるかを把握することが極めて重要です。徒手検査、姿勢評価、筋緊張のアセスメントを組み合わせて、解剖学的理解に基づいたアプローチが求められます。
また、TOSは神経学的・血管学的所見が重なり合うため、常に鑑別疾患(頚椎症、円回内筋症候群、肩関節疾患など)との見極めも重要です。
若手理学療法士や学生の方々は、まず3つのトンネルの構造と病態を明確にし、それぞれに対応した治療戦略を立てられるようにしましょう。
参考文献
- Sanders RJ, Hammond SL, Rao NM. Thoracic outlet syndrome: a review. Neurologist. 2007.
- Hoskins W, Pollard H. Thoracic outlet syndrome: a narrative review of the literature. Chiropr Osteopat. 2010.
- Hardy A, Jean-Luc G, et al. Pectoralis minor syndrome: anatomy, diagnosis, and treatment. J Shoulder Elbow Surg. 2012.